【2026年版】二次創作ガイドラインリンク集&一覧|許可・禁止の境界線を解説
※当サイトでは広告・アフィリエイトを利用しています。本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
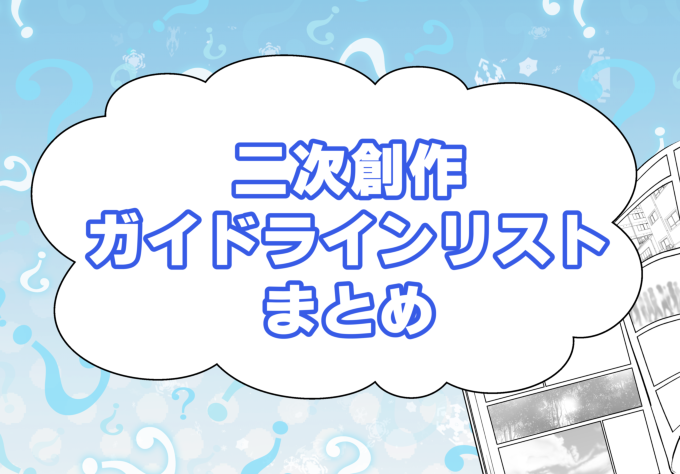
大好きなアニメやゲームのキャラクターで、自分だけの物語やイラストを創り出す「二次創作」。とっても楽しくて、創作意欲が刺激される活動ですよね!
でも、その一方で、「この作品って二次創作しても大丈夫なのかな?」「グッズを作って販売してもいいの?」「どこまでが許される範囲なんだろう…」と不安に思ったことはありませんか?
そんな時に必ず確認したいのが、原作の権利元(作者や会社)が出している「二次創作ガイドライン」です。
この記事では、
- なぜガイドラインの確認がそんなに大事なのか?
- ガイドラインはどこで探せる?見つけ方のヒント
- 読む時に絶対チェックしたい!共通の重要ポイント7つ
- 主要な人気作品・企業のガイドライン概要と公式リンク
- ガイドラインが見つからない・曖昧な時はどう考える?
といった内容を、二次創作初心者の方にも分かりやすく、具体的なキーワードも意識しながら徹底解説します。
この記事を読めば、二次創作のルールに関するモヤモヤが晴れ、自信を持って活動できるようになるはずです!
※この記事で扱う「二次創作」とは、主にファンが自身の技術や発想を用いて原作を元に新しい作品を創作する活動を指します。
近年話題の生成AIによる画像生成などについては、著作権やガイドラインの観点から異なる注意が必要となる場合があります。詳細は本文をご確認ください。
この記事は二次創作ガイドラインについて理解を深めるためのものですが、以下の重要な注意点を必ず読んでから、本文を読み進めてください。
- 一番大切なこと:公式の最新ガイドラインを自分で確認!
二次創作をするときは、必ず、あなた自身で、作りたい作品の「公式」が出している「最新」のガイドラインを直接読んで確認してください。
ルールを守ることが、トラブルなく創作を楽しむための基本です。 - この記事は「参考情報」です(法律アドバイスではありません)
この記事に書かれていることは、一般的な情報や、この記事を書いた時点(2026年1月)での情報です。
法律の専門家によるアドバイスではありません。(筆者も法律の専門家ではありません) - ガイドラインは「変わる」ことがあります
会社の考え方や状況によって、ガイドラインの内容は変更される可能性があります。
この記事の情報が、常に最新とは限りません。 - 活動は「自己責任」でお願いします
もし、この記事の情報だけを信じて行動し、何か問題が起きてしまった場合でも、当サイトでは責任を負うことはできません。
ご自身の判断と責任において、必ず公式の最新情報を確認し、ルールを守って二次創作を楽しんでください。
1.なぜ二次創作ガイドラインの確認が重要なのか?
二次創作は、あくまで「原作があってこそ」成り立つ活動です。
ガイドラインを確認することは、以下の点で非常に重要です。
- トラブルを避けるため: 知らずにルール違反をしてしまい、権利元から警告を受けたり、最悪の場合、法的措置を取られたりするリスクを防ぎます。
- 原作への敬意を示すため: ガイドラインは、権利元が作品やキャラクターを大切に思うからこそ設けているルールです。
これを守ることは、原作へのリスペクトを示すことにも繋がります。 - 安心して活動するため: ルールをきちんと理解していれば、「これは大丈夫かな?」とビクビクすることなく、安心して創作に打ち込めます。
- ファンコミュニティを守るため: 一部の人のルール違反が原因で、その作品全体の二次創作が禁止されてしまう…といった事態を防ぐためにも、一人ひとりがルールを守ることが大切です。ルール違反が継続されると作品全体が二次創作禁止になることがあります。
2.どこで探す?二次創作ガイドラインの見つけ方
では、ガイドラインはどこで確認できるのでしょうか? 主な探し方は以下の通りです。
- 公式サイトを徹底チェック! (最重要)
サイト内の「お知らせ/ニュース」「サポート/FAQ」「利用規約」などといった項目に記載されていることが多いです。サイト内検索も活用しましょう。 - 公式SNSを検索!
作品や企業の公式X(旧Twitter)アカウントなどで、ガイドラインに関する発表やリンクが投稿されている場合があります。
「作品名 ガイドライン」「会社名 二次創作」などで検索してみましょう。 - イベントの規約: 同人誌即売会などのイベントに参加する場合、イベント自体の規約で特定の作品の二次創作についてルールが定められている場合があります。
- ポイント:
検索エンジンで「(作品名) 二次創作 ガイドライン」「(会社名) 著作権」などと検索するのが基本です。
ガイドラインが見つかっても、それが最新のものか(更新日などを確認)も重要です。
3.ガイドラインを読む際の共通チェックポイント7つ
無事ガイドラインを見つけたら、次は内容をしっかり読み解きましょう。書き方は様々ですが、特に以下の7つのポイントに注目して確認すると、大事なことを見落としにくくなります。
3-1.まず確認!二次創作活動は「許可」されている?
そもそも二次創作活動が認められているのか、それとも「黙認」なのか、あるいは「禁止」なのかを確認します。
明確に「許可」されていれば安心ですが、「黙認」の場合はグレーゾーンも多く、より慎重な判断が必要です。
3-2.何を作ってOK?許可されている「範囲」(同人誌・グッズ等)
「二次創作OK」でも、作って良いものの範囲が限られている場合があります。
- 同人誌(漫画、小説、イラスト集など): 許可されていることが多いですが、規模(部数など)の制限がある場合も。
- 同人グッズ(アクキー、缶バッジなど): ここは特に注意が必要! 非営利でもグッズ制作自体を禁止していたり、アイテムの種類を限定していたりするケースが多いです。必ず確認しましょう。
- デジタル作品のネット公開: PixivやX(Twitter)へのファンアート投稿はOKか? 動画サイトは?
- コスプレ: 衣装制作、写真・動画公開は認められているか?
3-3.お金は関係ある?「営利目的」のルール(非営利・条件付き)
これが一番複雑で判断が難しいポイントかもしれません。
- 「非営利」限定か?: 利益を得る活動(販売など)が全面的に禁止されているか。二次創作を行うために発生した費用までを非営利としていたりする場合があります。
- 「趣味の範囲」はどこまで?: 材料費や印刷費程度の対価を得る「実費頒布」はOKとされる場合もありますが、その「範囲」の定義はガイドラインによって異なります。
- 具体的な基準はあるか?: 年間の売上上限額や販売個数などが定められている場合も。
- 当日版権: フィギュアなど立体物は原則NGでも、ワンフェスなどのイベントで当日版権を取得すればOK、という場合もあります。
「営利目的」の定義や線引きは非常に重要なので、慎重に確認しましょう。
3-4.これはNG!「禁止されている表現」(R-18/G・原作イメージ等)
ガイドラインで二次創作が許可されていても多くのガイドラインで共通して禁止されている表現があります。
- 原作・キャラクターのイメージを著しく損なう、貶めるような内容
- 公序良俗に反する内容(過度な性的表現 R-18、過度な暴力表現 R-18G など)
- 特定の個人、団体、人種、信条、宗教、政治などを攻撃・差別・中傷する内容
- 特定の政治・宗教活動への利用
- 公式作品であるかのように誤解させる表現(公式ロゴの無断使用など)
- 公式素材の無断使用
特にR-18/R-18G表現(いわゆる成人向け)の扱いは、「全面的に禁止」「ゾーニング(閲覧制限)すればOK」「非公開ならOK」など、対応が分かれます。必ず確認が必要です。
3-5.ロゴや画像は使っていい?「素材」の利用ルール
原作のロゴ、ゲーム画面、アニメ映像、音楽、音声などを自分の作品に使うことは、基本的にNGです。
公式が「ファンキット」などで二次創作利用OKとして提供している素材以外は、使わないのが原則と考えましょう。
3-6.書くべき?「クレジット表記」(権利者情報など)の必要性
作品によっては、二次創作物であることを明記したり、原作名や権利者名(例:「©会社名」)を表示するように定められている場合があります。
ガイドラインに指示があれば、それに従いましょう。
3-7.【要注意】生成AIの利用は許可されている?
最近急速に普及している生成AI(画像生成AIなど)を使って、その作品のキャラクターや世界観に基づいた画像を生成し、公開・利用することは許可されているでしょうか?
これは二次創作で最近発生している問題であり、権利元によって対応が大きく異なります。
- 明確な禁止・懸念表明: ガイドラインで生成AIの利用が明確に禁止されている、または権利元がAI利用に否定的な声明(例:「AI学習への利用を禁止する」など)を出している場合は、その意向を尊重し、絶対に利用してはいけません。
- 言及がない場合も慎重に: ガイドラインにAIに関する記載がない場合も安心はできません。生成AIの利用は、著作権や倫理的な側面で多くの議論があり、権利元の意向が不明な状況での利用は非常に高いリスクを伴います。
トラブルを避けるためには、AI生成物の利用は控えるのが最も安全な判断と言えるでしょう。 - 「二次創作」との区別: AIによる生成物を、ファンが主体的に創作する従来の「二次創作」と同列に扱って良いかは、権利元によっても見解が分かれる可能性があります。
安易に「二次創作」として公開・頒布することは避け、「AI生成である」ことを明記するなどの配慮が求められる場合もありますが、それ自体が許可されているかの確認がまず必要です。
4.【主要作品・企業別】二次創作ルールとガイドラインリンク集
ここでは、いくつかの人気作品や企業のガイドライン(または関連情報ページ)へのリンクと、各ガイドラインの「要点の要約」です。
文章は読みやすさのために短くしています。正式な条件・例外・定義は必ず公式原文で確認してください。
あくまで現時点での概要であり、参考情報です。繰り返しになりますが、ご自身の活動前に、必ず公式の最新ガイドラインを全文読んで確認してください。
東方Project(上海アリス幻樂団)
【参考】:東方Projectの二次創作ガイドライン
- 東方Projectの二次創作品を作成した場合、「東方Projectの二次創作である事の明記が必要」
- 東方Projectのイメージを損なう内容/公式コンテンツと誤解するような内容
- 他者の権利を侵害する、または侵害するおそれのある内容
- 原作のゲーム素材使用やエンディングを公開する行為
- 原作や二次創作を使用して個人の思想を発信する行為
- その他の過剰な性的表現や特定の個人や団体などを中傷する行為
- ZUN本人の許可無く、本人の写真を加工・公開する行為
原神(HoYoverse)
HoYoverseのHoyoLABの【参考】:原神公式でアナウンスされているガイドライン
個人または法人格のない団体は、非営利目的に限り、原神のゲームを題材とした二次創作物の制作、展示、頒布および公開についてのガイドラインが出ています。
下記の展示、頒布、公開
- イラスト、マンガ、小説などの同人誌の制作
- キャラクターのコスプレ衣装の制作
- キャラクターのコスプレ写真・動画の制作
- 原神のグッズ、モチーフ料理などの制作
- 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用
- 公式作品(あらゆるもの)を直接二次利用すること、またはスキャン・トレース等
- コンテンツのイメージを損なう又は第三者の名誉・品位等を傷つけると判断されるもの
- HoYoverseの関係者と誤解を与えたり、公式制作物であるかのように誤解をあたえるおそれのあるもの
- 法令または公序良俗に反するおそれのあるもの
ゼンレスゾーンゼロ(HoYoverse)
HoYoverseのHoyoLABの【参考】:ゼンレスゾーンゼロ公式でアナウンスされているガイドライン
個人または法人格のない団体は、非営利目的に限り、原神のゲームを題材とした二次創作物の制作、展示、頒布および公開についてのガイドラインが出ています。
- 個人または法人格のない団体が、利益を得ることを目的とせずに二次的著作物を制作する場合
- 趣味の範囲で利用し、原材料費等の制作にかかった費用程度の対価を得る場合
下記の展示、頒布、公開
- イラスト、マンガ、小説などの同人誌の制作
- キャラクターのコスプレ衣装の制作
- キャラクターのコスプレ写真・動画の制作
- ゼンレスゾーンゼロのグッズ、モチーフ料理などの制作
- 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用
- 公式作品(あらゆるもの)を直接二次利用すること、またはスキャン・トレース等
- コンテンツのイメージを損なう又は第三者の名誉・品位等を傷つけると判断されるもの
- HoYoverseの関係者と誤解を与えたり、公式制作物であるかのように誤解をあたえるおそれのあるもの
- 法令または公序良俗に反するおそれのあるもの
崩壊学園、崩壊3rd(株式会社miHoYo)
【参考】:株式会社miHoYoの二次創作に関するガイドライン
【参考】:HoYoverseのHoyoLABの崩壊3rd公式によるガイドライン
ガイドラインの遵守事項を遵守している場合に限り、個人に対しては著作権侵害を主張しないようです。
- イラスト、同人誌、漫画、小説などの作成、各種の運用
- 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用
- 公式コンテンツの素材を直接二次創作品へ利用すること(スキャン/トレースを行うこと)
- 株式会社miHoYoのコンテンツのイメージ著しく損なうこと
- 第三者の名誉や品位を傷つけると判断されるもの
- 過度な公序良俗に反したり、反社会的な表現を含むこと
- 第三者に版権が帰属するコラボ作品の利用全般
ブルーアーカイブ、アズールレーンなど(株式会社Yostar)
【参考】:株式会社Yostarの「ブルーアーカイブ」二次創作に関するガイドライン
【参考】:「アズールレーン」二次創作に関するガイドライン
【参考】:「アークナイツ」二次創作に関するガイドライン
株式会社Yostarが定める「非営利目的」の場合に限り個人または法人格のない団体は「ブルーアーカイブ・アズールレーン」を題材とした二次創作物(同人誌、同人グッズなど)の制作や配布/頒布などを自由に行うことが出来るようです。
- 個人または法人格のない団体で非営利が目的である
- 日本国内での発表および流通の場合
- 趣味の範囲で利用し、継続的な創作活動のためツール類や原材料費などの制作に必要な費用程度の対価・利益を得る場合は非営利目的の範囲のようです。
- イラスト、フィギュア、人形その他の立体工作物の作成、展示、配布
- 同人誌や二次創作デジタルコンテンツの作成、展示、配布、配信
- クリエイターファンコミュニティサービスにおける二次創作作品の掲載
- 株式会社Yostarのゲームイメージを逸脱/イメージを損なう内容
- 公序良俗に反する内容
- 直接的にゲームコンテンツ素材のコピー、スキャン、トレース等を使用し創作性が無いまたは低い物
- 公式として詐称する活動
- 他社の権利を侵害している、侵害する恐れのある内容
- 公式製品のように誤解を招くおそれがある内容
ウマ娘 プリティーダービー(株式会社Cygames)
【参考】:株式会社Cygamesの「ウマ娘 プリティーダービー」二次創作に関するガイドライン
「ウマ娘 プリティーダービー」は実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが多く存在しており、馬名を馬主から使用許可を出してもらったことなどにより実現した作品です。
二次創作自体のファン活動自体は否定していないようですが、ガイドラインの遵守が必要です。
やむを得ない場合は法的措置を検討する場合もあると記載されています。
- ウマ娘 プリティーダービー、または第三者の考えや名誉を害する目的のもの
- 暴力的・グロテスク・性的描写を含むもの
- 特定の政治・宗教・信条を過度に支援、または中傷などをすること
- 反社会的な表現
- 第三者の権利を侵害するもの
二次創作活動自体は否定されていないので非常に厳しい内容ではなさそうです。
しかし、二次創作で一番違反しやすそうな箇所としては「性的描写」が挙げられます。
「過度や過剰な性的描写」ではなく「性的描写」と記載されているのでR-18にイラストは全て禁止として考えるのが妥当です。
NIKKE(SHIFT UP CORP.)
【参考】:SHIFT UP CORP.の「NIKKE」二次創作に関するガイドライン
- 基本的には非営利のみ許諾
- 個人や法人格のない団体がコンテンツ共有プラットフォームで二次創作物を公開し収益を得ること。ガイドライン違反した内容があった場合は収益化の中止を求める場合あり
- 趣味の範囲で二次創作の販売をすること
- 立体の造形物を販売する場合は個人や法人格のない団体が、「当日版権制度」を採用したイベントに参加する場合は販売許諾の検討が行われる。(イベントが定める手順に沿っての申請が必要)
通常のファン活動や同人活動の域を超えた営利目的を主体として活動を行った場合、二次創作物の制作や販売、頒布は禁止されています。数量や収益の規模に基づいて「SHIFT UP CORP.」が判断するようです。
二次創作を公開する場合は二次創作であることを明確にするために同人誌やグッズのいずれかの場所に「使用コンテンツ名(原作名)」と「著作権者情報(SHIFT UP CORP.)」の明記が必要です。
月姫,FGO,魔法使いの夜(TYPE-MOON)
二次創作の作品ごとで対応方法が異なるため、注意。
- 作品の画像や映像コピー、取り込み、トレースなどをして使用(自分で描いた二次創作はOK)
- TYPE-MOONのロゴや作品の関連商品に類似した装丁やパッケージの制作
- 引用の域を超えたシナリオの書き起こし
- 音声や音楽のコピー取り込み
- 同人誌と同人ゲームは禁止事項を確認して違反しない場合は制作と頒布はOK
- 同人グッズは「同人活動」の域を超えなければOK、明らかに商業目的での制作頒布など「同人活動」の域を超えている場合は禁止
- 立体物は禁止、当日版権システムによるイベントに関しては各イベントの運営ルールを確認
ドールズフロントライン(株式会社サンボーンジャパン)
【参考】:株式会社サンボーンジャパンのコンテンツ利用に関する
- 個人または法人格のない団体が非営利目的の場合においては自由に二次創作活動は可
- イラスト、フィギュア、人形その他の立体工作物の作成、展示配布
- 同人誌の作成、展示、配布
- コスプレ衣装の作成、展示配布など
- 原材料費(人件費を含めない)を回収する範囲から逸脱しファンとしての趣味の範囲を超えている場合。
以下の条件を満たす物は非営利目的を超える範囲でも例外的に許容されている
同人誌:取引実態や社会通念などを勘案して、概ね過度な営利性がないものと通常判断ができるような行為
フィギュアなどの立体工作物:原材料費(人件費含めず)を超えた場合でも、得られた対価が10万円程度までと判断されるような行為。ワンフェスなどの個別約定がされているような場合は別途判断
アクリルスタンド、キーホルダーなどのグッズ:非営利を超える範囲での二次創作活動は認められていない。ワンフェスなどの個別約定がされているような場合は別途判断
- ゲームイメージを逸脱するもの
- 株式会社サンボーンジャパンのゲームイメージを損なう内容
- 公序良俗に反する内容
- ゲームのコンテンツを直接コピー、スキャン、トレース等を使用するなど創作性が乏しい物
鳴潮(KURO TECHNOLOGY CO., LIMITED)
【参考】:鳴潮ー二次創作ガイドライン
- 個人または法人格のない団体が非営利目的の場合においては自由に二次創作活動は可
- イラスト、フィギュア、人形その他の立体工作物の作成、展示配布
- 同人誌の作成、展示、配布
- コスプレ衣装の作成、展示配布など
- 趣味の範囲で利用し、原材料・ツール類などの制作にかかった費用を回収する場合であれば非営利目的の範囲内
- コンテンツのイメージを逸脱する、又はイメージを損なう内容
- 第三者の権利を侵害する、または公序良俗に反する内容
- 直接的にコンテンツの素材をコピー、スキャン、サンプリング、トレース等で使用するなど、創作性が無いまたは低いもの
- 公式と詐称しての活動、関係者と誤解されるかのような印象を与えるような内容
- その他KURO TECHNOLOGY CO., LIMITEDが不適切と判断した内容
5.ガイドラインが見つからない・曖昧な場合はどう考える?
「好きな作品のガイドラインが見つからない…」「読んだけど、自分の活動がOKかどうかの判断が難しい…」そんな時、どうすれば良いのでしょうか。
- 【重要】基本は「ガイドラインに書かれている範囲で判断」が前提です:
「直接聞けば確実では?」と考えてしまうかもしれませんが、二次創作に関するファンからの個別の問い合わせに、企業や原作者が対応することはまずありません。
問い合わせが多数寄せられると、本来の業務の大きな妨げになってしまい、大変な迷惑となります。
「公開されている情報(ガイドライン)が全てです」「個別のお問い合わせには回答できません」というのが基本的なスタンスです。
ただし、企業が問い合わせ窓口や申請フォームを用意している場合は、その案内に従ってください。 - ガイドラインがない=「許可されていない」と考えるのが基本:
では、どう判断すれば良いのでしょうか? 残念ながら明確な答えはありませんが、最も安全で推奨される考え方は、「明確なガイドラインや許諾がない限り、二次創作(特に営利目的の活動、原作のイメージを変える可能性のある表現、公式と誤認されかねないもの)は、基本的に『許可されていない』と考える」ということです。
これがトラブルを未然に防ぐための基本的なスタンスになります。 - グレーゾーンは避けるのが賢明:
判断に迷うような活動、つまり「グレーゾーン」と思われるものは、控えるのが最も賢明な判断です。
個人が趣味の範囲で非営利のファンアートをSNSに投稿する程度に留めておくのが、多くの場合、比較的安全な範囲と言えるかもしれませんが、それも保証されるものではありません。 - 他の人の活動は参考にしない:
「他の人もやっているから大丈夫だろう」という考えは危険です。その活動がルール違反である可能性も十分にあります。
周りに流されず、常にご自身の責任で判断することが求められます。 - 特に、生成AIの利用のように新しい技術に関わることや、著作権・倫理的に様々な意見がある分野については、権利元の意向が明確でない限り、安易に「大丈夫だろう」と判断せず、利用を控えるのが賢明と言えるでしょう。
最終的には、「この二次創作活動を、原作者や権利元が見たらどう思うだろうか?」と、相手の立場や気持ちを想像し、原作への敬意を払って慎重に行動することが、何よりも大切です。
まとめ
二次創作は面白く楽しいですが、原作があってこその活動です。
トラブルなく、長く楽しく創作を続けるためには、公式が出している「二次創作ガイドライン」をきちんと確認し、理解することが欠かせません。
- 公式サイトなどで最新情報を必ず探そう。
- 「許可範囲」「営利」「禁止表現」「素材利用」「クレジット」「生成AI利用」などをしっかりチェック!
- 作品ごとにルールは違うので、思い込みは禁物。
- ガイドラインが不明な場合は問い合わせはせず、「許可されていない」と考え慎重に判断しよう。
ガイドラインをしっかり理解し、原作へのリスペクトの気持ちを持って活動すれば、きっとあなたの二次創作活動はより豊かで、実りあるものになるはずです。
特に生成AIの利用については、権利元の意向を最大限尊重し、ガイドラインの有無に関わらず、非常に慎重な判断が必要です。
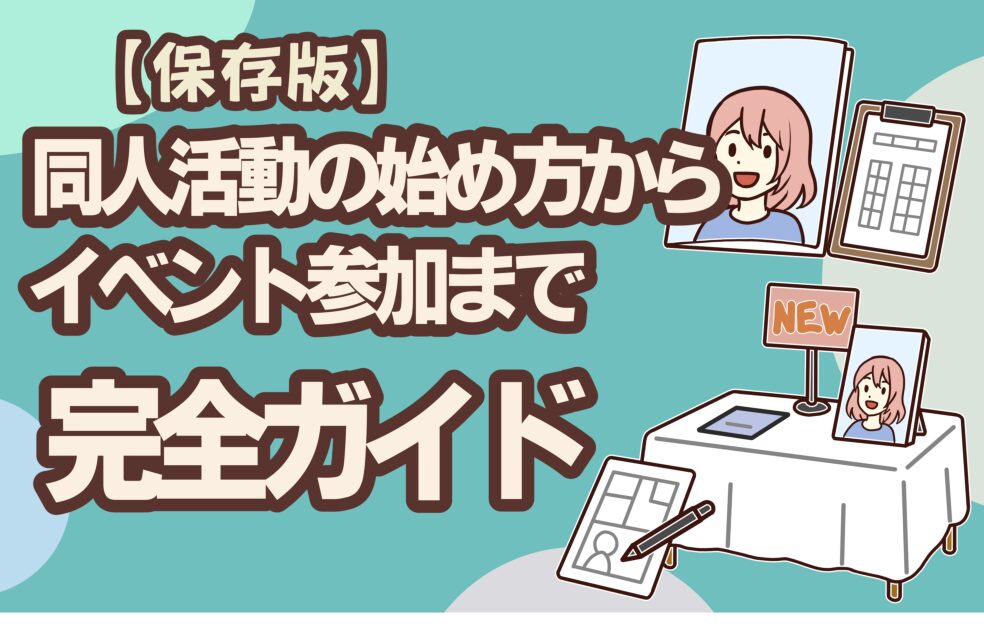
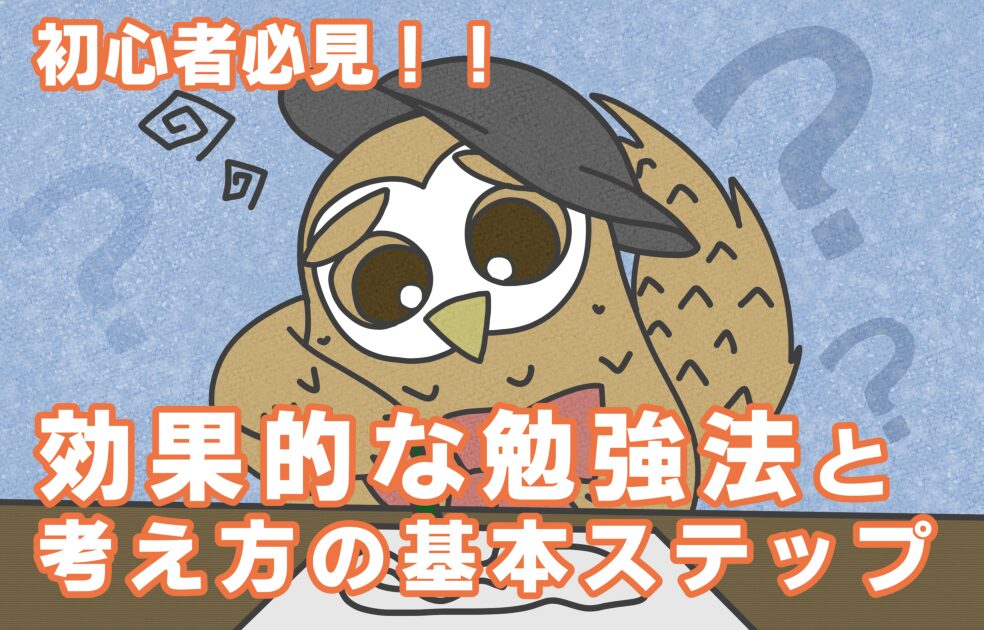











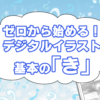
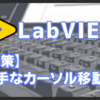
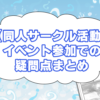

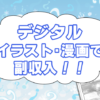
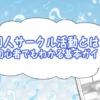

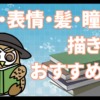
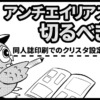
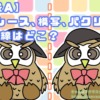
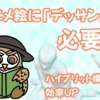
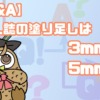
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません