光と影が上達する!イラストのライティングおすすめ本を目的別に紹介
※当サイトでは広告・アフィリエイトを利用しています。本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
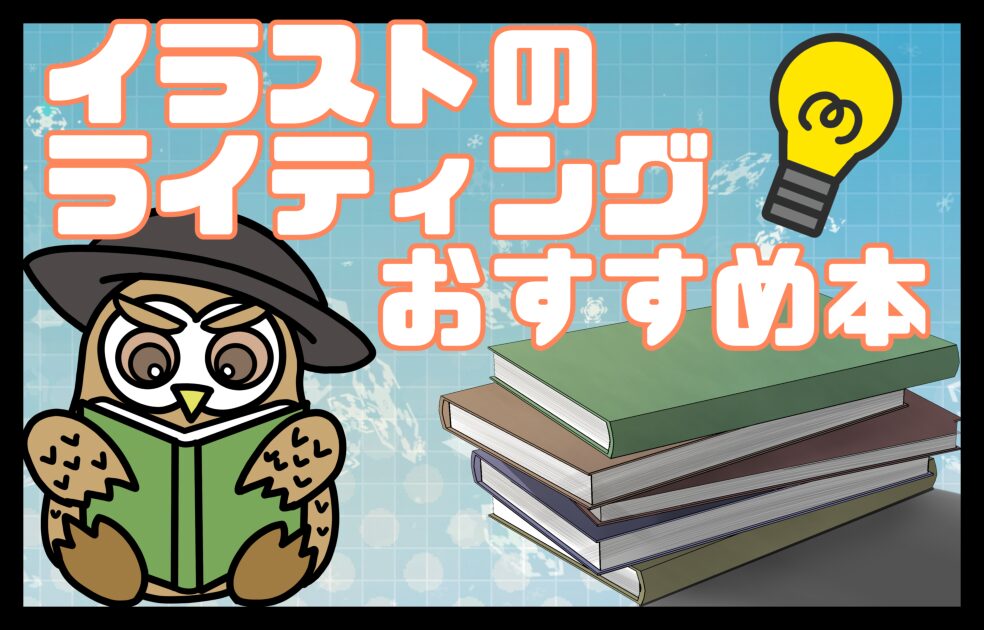
あなたの絵を「のっぺり」から「立体的」に変える一冊
「光と影の理屈はわかったけど、いざ塗るとなると自信がない…」 「キャラクターに立体感が出ず、なんだか作品がのっぺりしてしまう…」
そんな悩みを抱えていませんか?その悩みは、「光と影」について解説された優れた「教科書」を手にすることで、大きく改善できます。
きゃんばすクラスタでは、すでに光の「理論(Why)」と影の「実践(How)」について、以下の記事で解説しています。
この記事は、その次のステップとして、「もっと深く学びたい」「プロのテクニックを知りたい」というあなたのための、「教材」をまとめたものです。
数ある書籍の中から、あなたの目的やレベルに合った最適な一冊が必ず見つかるように、解説します。あなたにぴったりの一冊を見つけて、光と影を完全にマスターしましょう!
「光と影」の本、どう選ぶ?挫折しないための3つのチェックポイント
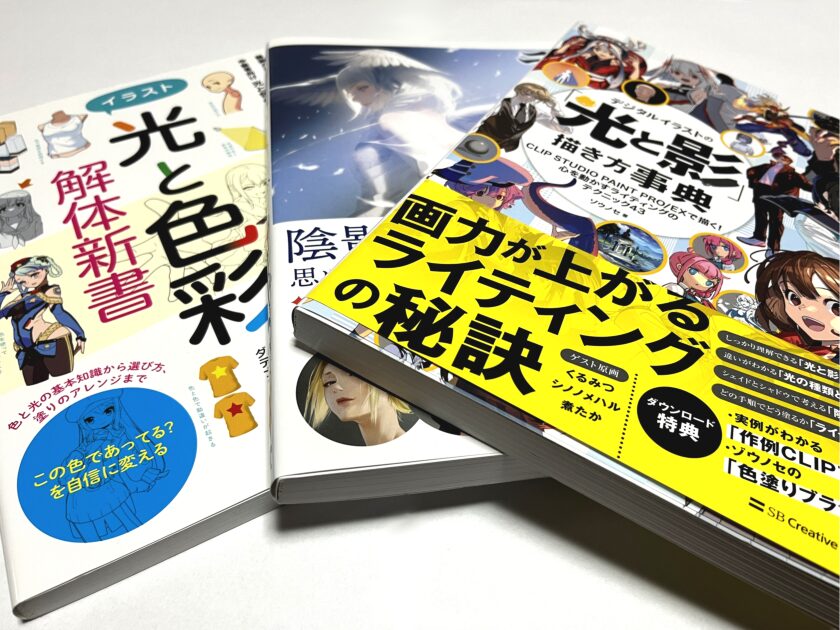
光と影に関する本は、専門的で難解なものも多く、選び方を間違えると挫折の原因にもなります。購入後に後悔しないために、以下の3つのポイントで、自分に合った本かを見極めましょう。
①「理論」中心か、「実践(塗り)」中心か?
理論中心: 「なぜ影はそう落ちるのか」「光の原理原則」といった「Why」を深く学びたい人向け。
実践中心: 「どうやって塗るのか」「レイヤー構成」といった「How」をすぐに知りたい人向け。
もちろん、両方を解説した本もありますが、どちらの比重が大きいかを意識して選ぶと失敗がありません。
② 今の自分の「レベル」に合っているか?
初心者向け: 図解が多く、専門用語が噛み砕いて解説されている本。まずはイラストの立体感を出すことを目標にします。
中〜上級者向け: 物理法則や色彩理論など、より専門的な内容に踏み込み、リアルな表現を目指す本。
③「教科書」として長く使いたいか、「事典」として引きたいか?
教科書タイプ: 基礎から応用まで、順を追って体系的に学べる構成。一冊通して読むことで力がつきます。
事典タイプ: 豊富な作例やテクニックが網羅されており、悩んだ時に必要なページだけを開いて参考にするのに適しています。
理論と実践をバランス良く学べる入門書籍
光と影のイラスト表現を学ぶ!ライティングの教科書
イラストの「光と影(ライティング)」と「色彩」について、基本の理論と実践的なテクニックを解説しています。
本書では、難しい理論を「スパイス」として捉え、肌や金属といった素材別の描き方や角度別サンプルなども紹介しています。読者は、説得力と魅力のあるイラスト表現を学ぶことができます。
発行日:2024年8月27日
ページ数:248ページ
出版社:ソーテック社
- 色やライティングの基本理論を、分かりやすく解説。
- 肌、髪、金属、レザーなど、素材ごとの質感の描き方を紹介。
- 理論どおりでなくても、イラストとして印象的に見せるテクニックも学べる。
- イラストにもっと臨場感や説得力を出したいと思っている方。
- 光と影、色の基本的な使い方を効率よく学びたい方。
- 肌や金属など、いろいろな素材の質感を描き分けたい方。
光と色のチュートリアル
デジタル彩色における「光と色」の知識やコツを解説する技法書です。
本書では、光の性質や色の仕組みといった基礎理論から、具体的な彩色のテクニックまでをぎゅっと詰め込んでいます。
読者は「なぜそう見えるか」を理解することで、色塗りがいつも同じになる悩みや、迫力が出ない悩みを解決し、魅力的なイラストが描けるようになります。
発行日:2021年12月7日
ページ数:204ページ
出版社:マール社
- 光と色の基本的な仕組みや理論から学べる
- 自然光、室内照明、ネオンなど、さまざまな環境での光と色の違いを紹介
- セル画塗り、グレージング、レンダリングなど、多様なデジタル彩色技法を掲載
- イラストの色塗りがいつも同じような雰囲気になってしまう方
- 描いたイラストに立体感や迫力を出したいと思っている方
- 光や色の理論を基礎からしっかり学びたい方
具体的な「塗り」のテクニックを学ぶ実践書籍
デジタルイラストの「光と影」描き方事典
イラストにおける「光と影」の描き方を事典形式で解説しています。
光の基本的な考え方から、CLIP STUDIO PAINTを使った具体的な塗り方(ライティング)まで、説得力のある絵作りのテクニックを紹介しています。
読者は本書を通じて、光を意識した陰影表現を基礎から実践まで学ぶことができます。
発行日:2024年3月1日
ページ数:176ページ
出版社:SBクリエイティブ
- イラストにおける光と影の基本ルールを、わかりやすく解説。
- 「陰(シェイド)」と「影(シャドウ)」の違いなど、陰影の捉え方が学べる。
- CLIP STUDIO PAINTを使った、狙った光を表現するための具体的な塗り手順を紹介。
- 著者が使う「色塗りブラシ」と、様々なライティング実例の「作例CLIPファイル」をダウンロードできる。
- 影の付け方や光の表現に自信がなく、説得力を出したい方。
- ライティングの知識や理屈を、基礎からしっかり学びたい方。
- 雰囲気のある、ワンランク上のイラストを描きたいと考えている方。
イラスト<光と色彩>解体新書
人気イラスト講師のダテナオト氏が、イラストの「光と色彩」について解説する技法書です。
本書では、線画を描いた後の「塗り」に焦点を当て、配色の基本、光と影(ライティング)の表現、仕上げのテクニックまでを丁寧に紹介しています。
読者は、色塗りの基礎知識や作例を学ぶことで、イラストの完成度を高めることができます。
発行日:2022年10月11日
ページ数:144ページ
出版社:マイナビ出版
- 「配色編」「ライティング編」「テクニック編」に分かれ、順を追って学べる
- 光と影の三面関係や、失敗しない影色の選び方など、基礎から紹介
- 「よくあるNG例」とその対処法が分かり、失敗を減らせる
- 線画は描けるけれど、色塗りの工程でいつも悩んでしまう方
- 配色やライティングの基本を、改めてしっかり学びたい方
- 自分のイラストがのっぺりして見えるのを改善したい方
プロを目指すための、専門的な理論・上級書籍
色と光マスターガイド イラスト上達のための理論と実践
「色彩と光の仕組み」を深く掘り下げる、理論と実践の教科書です。
本書は、前半の〈理論〉パートで専門知識を学び、後半の〈実践〉パートで海外のプロがどう応用しているかを解説します。
本書を通じて、読者はプロの現場でも通用する、デジタル・アナログ問わず応用可能な高度な知識と思考法を身につけることができます。
発行日:2023年1月31日
ページ数:388ページ
出版社:マール社
- 色彩理論や光の仕組みといった専門知識を「理論編」で深く学べる。
- 光と影(カゲ)をうまく使い、望み通りの形や質感を表現する方法がわかる。
- 空気遠近法や表面下散乱など、上級者向けのトピックスも解説。
- イラストの技術をさらに高めたいプロや、プロを目指している方。
- 光と色の仕組みを、感覚だけでなく理論から深く理解したい方。
- 学んだ理論を、実際のイラスト制作にどう活かすか知りたい方。
画づくりのための光の授業
イラストやCGなどビジュアル制作に携わるクリエイターに向けた、「光」の教科書です。
本書では、自然光や人工光の基本原理、色の仕組み、影の描き方、さらには構図や演出での光の使い方を、豊富な写真やCG、イラスト例と共に解説しています。
読者は、光の仕組みを基礎から学び、説得力のある作品作りに活かすことができます。
発行日:2019年10月23日
ページ数:358ページ
出版社:ビー・エヌ・エヌ新社
- 自然光と人工照明の基本的な特性を解説
- 拡散反射、鏡面反射、透明度など、光と物質がどう作用するかを紹介
- 光を科学と芸術の両面から学ぶことができる教科書的な内容
- 光と影の基本的なルールを、基礎からしっかり学びたい方。
- 作品に立体感や説得力を出したいと思っている方。
- 光を使って、イラストや映像のムードや感情を表現したい方。
カラー&ライト ~リアリズムのための色彩と光の描き方
アメリカの有名イラストレーター、ジェームス・ガーニー氏が解説する「色彩と光」の教科書です
本書では、リアリズム絵画に必要な光の性質や色の理論、配色方法、それらの相互作用などを、豊富なイラストと共に紹介しています。
読者は、アートやゲーム、映画など分野を問わず、説得力のある作品を描くための基礎知識を学ぶことができます。
発行日:2012年1月30日
ページ数:224ページ
出版社:ボーンデジタル
- 光の性質や色の仕組みといった、絵画の基礎理論が学べる
- 見開き2ページで1トピックという、読みやすく分かりやすい構成
- 手描き・デジタル問わず、すべてのアーティストに役立つ内容
- リアルで説得力のある絵を描きたいと思っている方
- 光と色の理論を、基礎から体系的に学びたい方
- イラスト、ゲーム、映画など、様々な分野でビジュアル制作に関わる方
まとめ:理論と実践を繋げ、光を味方にしよう
「光と影」に関するおすすめの書籍を、3つのカテゴリに分けて紹介しました。
あなたの現在のレベルや、「理論が知りたい」「実践テクニックが知りたい」といった目的に合わせて、最適な一冊を選ぶ参考にしてみてください。
きゃんばすクラスタでは、光と影に関する理論と実践テクニックも、それぞれ以下の記事で解説しています。 書籍で得た知識と合わせて読むことで、より理解が深まるはずです。
光を論理的に理解し、味方につけることで、あなたのイラスト表現は必ず次のレベルへと引き上がります。
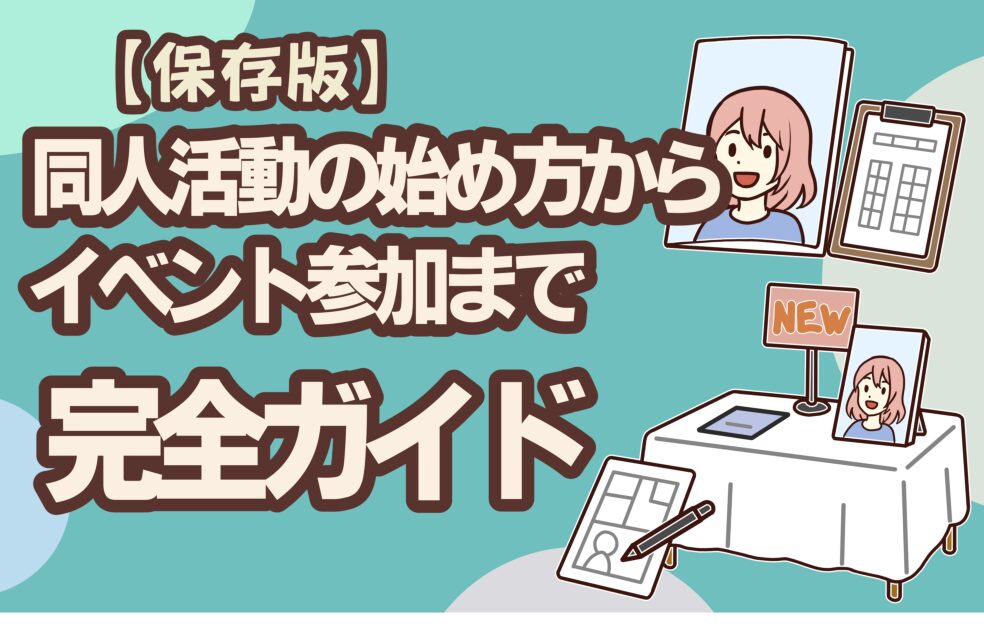
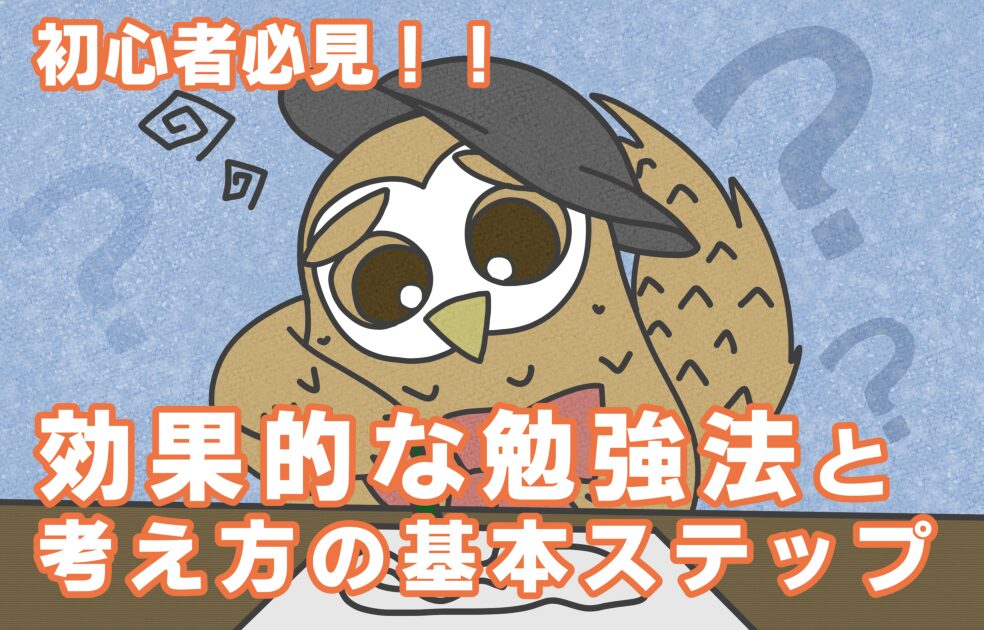








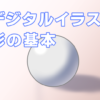


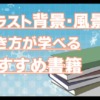
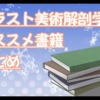
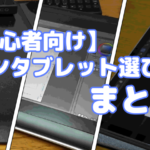

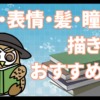
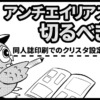
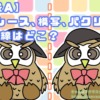
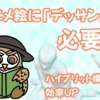
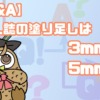
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません