【読んだけど忘れる人へ】イラスト技法書の知識を「画力」に変える勉強法
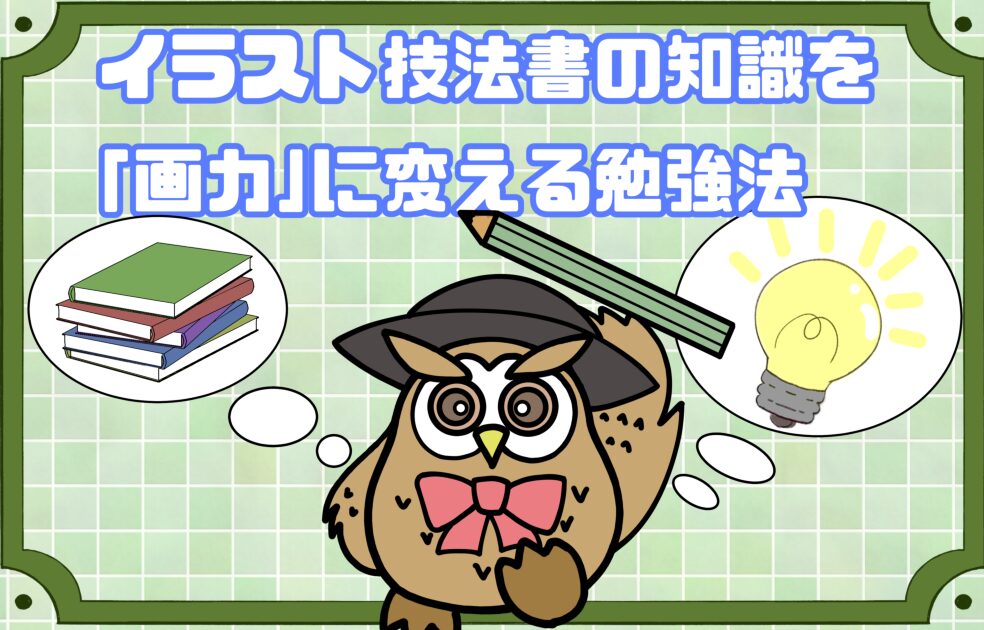
「もっと上手くなりたい!」と思って、イラストの技法書や美術解剖学の本を買ってみたものの…
「読んだけど、ほとんど内容を覚えていない…」
「知識としては『なるほど』と思ったけど、いざ描く時に全く活かせない…」
「結局、本棚の肥やしになってしまっている…(積ん読状態)」
こんな経験はありませんか?
せっかくの素晴らしいイラストの参考書も、ただ読むだけではなかなか自分のスキルにはなりません。
しかし、物事を効率的に覚えるための、ちょっとした工夫と効果的な学習法を知るだけで、本の知識をあなたの「描く力」として、着実に定着させていくことができます。
この記事では、イラストの技法書や解説書を最大限に活用するために、分かりやすく解説していきます。
- なぜイラスト参考書を読んでも「わかったつもり」で終わってしまうのか
- 記憶に残りやすい、効果的とされる3つの学習の考え方
- 明日からできる!イラスト参考書の具体的な学習サイクル
- あなたのタイプに合わせた、おすすめの学習プラン
特別な才能は必要ありません。この記事を参考に、あなたの持っているイラスト参考書を「最強の味方」に変えて、楽しく、そして確実に上達への道を歩んでいきましょう!
そもそも、どんな本を選べば良いか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
1.はじめに:「読んだけど忘れる…」を卒業!効率的な学習法を味方につけよう
イラストが上手くなりたいという気持ちで技法書を手にしたあなたは、すでに素晴らしい一歩を踏み出しています。
しかし、多くの人が「本を読んだけど忘れてしまう」「実践できない」という壁にぶつかります。
これは、あなたの記憶力ややる気の問題だけではありません。多くの場合、物事を覚える仕組みに沿っていない、非効率な学習法が原因なのです。
この記事では、大げさな精神論ではなく、イラストの参考書で学んだことを効率的に身につけるための、誰にでも実践できる考え方と具体的な方法をご紹介します。
学習成果には個人差がありますが、この記事で紹介するヒントを取り入れることで、きっと今よりも学習の手応えを感じられるようになるはずです。
2.なぜ?イラスト参考書を読んでも「わかったつもり」で終わってしまうのか

対策を考える前に、まず「なぜイラストの本を読んでも忘れてしまうのか」を知っておきましょう。
- 「見る」だけの受動的な学習だから:
ただ目で文字やイラストを追うだけでは、情報は頭を素通りしやすく、記憶に定着しにくいのです。 - 「わかる」と「描ける」は全く別のスキルだから:
本を読んで「なるほど、こう描くのか」と理屈を理解すること(知識)と、それを自分の手で再現すること(技術)は、スポーツ観戦と実践のように、全く別の訓練が必要です。 - イラストと文章、片方しか見ていないから:
イラスト解説が豊富な本なのに、文章だけを読んでイラストをじっくり見なかったり、逆にイラストだけ見て大切な解説を読み飛ばしたりすると、情報の半分しかインプットできていません。これも「わかったつもり」になる大きな原因です。 - 人間の記憶は「忘れる」のが当たり前だから:
私たちの頭は、全ての情報を記憶していたらパンクしてしまいます。そのため、重要ではないと判断された情報は、時間と共に忘れていくのが自然な仕組みなのです。
3.イラストの本の知識を「使えるスキル」に変える3つのポイント
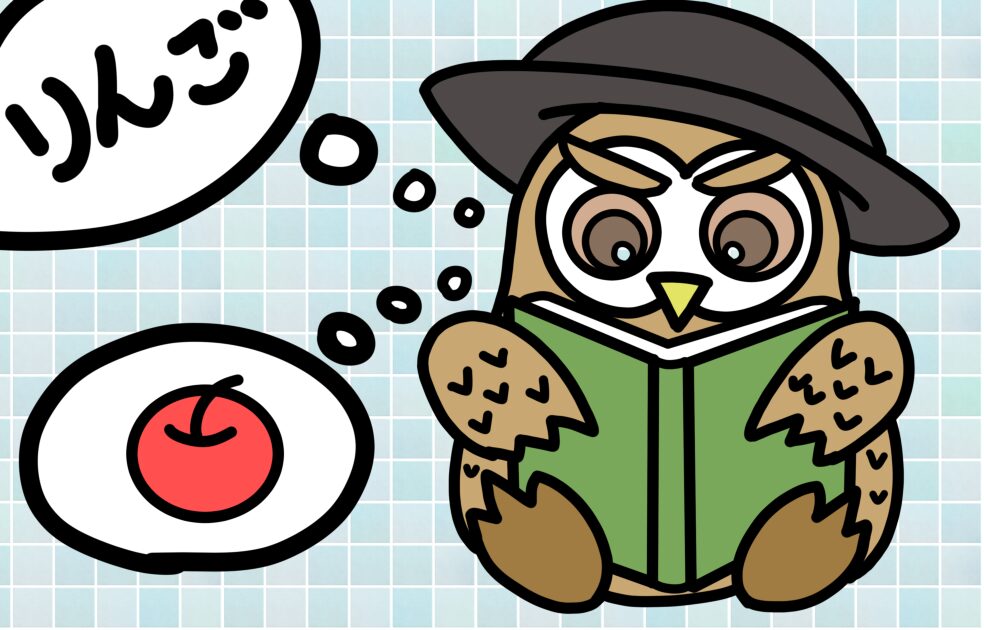
では、どうすれば記憶に残り、実践できるスキルになるのでしょうか?その鍵となる、学習効果を高めるための3つの考え方(ポイント)を、イラスト学習に置き換えて簡単に解説します。
ポイント1:言葉とイメージをセットで覚える「二重の記憶」
考え方:
私たちの頭は、言葉の情報(テキスト)と言語以外の情報(イラスト・イメージ)を別々の方法で記憶しようとします。この両方を同時に働かせることで、記憶がより強固になり、忘れにくくなると言われています。
イラスト学習での応用:
- イラストを言葉にする: 技法書のイラストだけを見て、「これは腕の筋肉がこうなっていて…」「光が左上から当たっているから影はここに…」と、自分の言葉で声に出して説明してみます。
- 文章をイメージする: 解説文を読みながら、その内容を表すイラストを頭の中で思い浮かべます。
ポイント2:頭をしっかり使う!「自分の言葉や絵で作り出す」学習法
考え方:
情報を受け取るだけでなく、自ら情報を「生成」する、つまり自分の頭で考え、情報を再構築することで、学習効果は飛躍的に高まります。
イラスト学習での応用:
- 自分で描いてみる: 参考書のイラストを一度隠し、解説文だけを頼りに、自分なりに簡単な図やイラストを描いてみます。
完璧に描く必要はありません。「描く」という行為自体が、学んだことを深く理解する助けになります。 - 自分で解説してみる: イラストやテキストを見ながら、「なぜこのイラストはこのような形なのか?」「この矢印は何を意味しているのか?」と自分自身に問いかけ、その答えを説明します。
ポイント3:何度も「思い出す」練習で記憶を強化する
考え方:
記憶は、本を読み返す(インプット)ことよりも、内容を「思い出す」(アウトプット)ことによって強化されます。定期的に記憶を引き出す練習が、長期的な定着に繋がります。
イラスト学習での応用:
- イラストから解説を思い出す: 書籍のイラストだけを見て、関連するキーワードや解説文を思い出します。
- 解説からイラストを思い出す: 解説文を読み、その内容を表すイラストがどんな図だったかを具体的に思い出します。
4.【実践編】誰でも出来る!イラスト参考書の効果的な学習ステップ
上記の3つのポイントを、日々の学習にどう取り入れれば良いか、具体的なステップをご紹介します。
Step1:学習の準備(ポモドーロ・テクニックと「ふせん」)
- 集中時間を作る: 人間の集中力は長く続きません。「25分集中+5分休憩」を1セットとする「ポモドーロ・テクニック」などを活用し、「まず25分だけ頑張る」と決めて机に向かうと、学習を始めるハードルが下がります。
- 「ふせん」を用意する: 「ふせん」は、ただの目印ではありません。能動的な学習ツールとして活用できます。
Step2:インプット(「なぜ?」を考えながら読む)
ただ漫然とイラスト参考書を読むのではなく、「なぜ?」「どういうこと?」と疑問に思った箇所に質問を書いた「ふせん」を貼りながら、考えながら書籍を読み進めます。
Step3:アウトプット(「描く」「説明する」で記憶を自分のものに)
読んだ範囲の重要なイラストについて、本を閉じて(あるいは隠して)自分で描き写してみたり、そのイラストが何を説明しているのかを声に出して説明したりしてみましょう。これが最も記憶に残りやすい方法です。
Step4:記憶の定着(効果的な復習と「睡眠」)
一度で覚えようとせず、適切なタイミングで復習することが記憶定着の鍵です。「完全に忘れる前」に復習するのが最も効率的と言われています。
- 復習のタイミング例: 1日後、3日後、1週間後…というように、少しずつ間隔を空けて、Step3のアウトプット(描く、説明する)を繰り返します。
- 睡眠を味方につける: 記憶は睡眠中に整理・定着します。徹夜で詰め込むよりも、学習後に質の良い睡眠をとる方が、結果的に記憶に残りやすくなります。
このように学習を『続ける』ための、より具体的な工夫や考え方については、こちらの記事もきっと役立つはずです。
5.【タイプ別】あなたに合った学習プランを見つけよう
全てを完璧にやるのは大変です。ご自身の目的や性格に合わせて、プランを組み合わせてみてください。
プランA:じっくり深く理解し、長期的に活かしたいあなたへ
- 戦略: 自分の言葉で再構築し、深く理解することを重視。
- 方法: 「質問ふせん」で疑問を洗い出しながら読み、各章ごとに重要なイラストを自分で描き写しながら、その解説を自分の言葉でノートに要約していく。復習は、そのノートを見返したり、再度説明したりする。
プランB:勉強が苦手…まずは「続ける」習慣をつけたいあなたへ
- 戦略: 負担の少ない方法から始める。
- 方法: 「まず25分だけ」と時間を区切り、気になったイラストの横に「すごい!」「ここが重要」「あとで調べる」といった一言感想を「ふせん」に書いて貼ることから始めてみる。
完璧に理解しようとせず、「今日はこの1章を最後まで読み通す」といった低い目標を立て、達成感を味わうことを優先する。
6.まとめ:イラスト参考書を最強の味方にして、着実な上達を楽しもう!
イラストの技法書や参考書は、ただ読むだけでは「知識」が増えるだけかもしれません。
しかし、今回ご紹介したような効果的な学習法を取り入れ、能動的に本と向き合うことで、その知識をあなたの「描く力」へと変えていくことができます。
- ただ「見る」だけでなく、「言葉で説明」したり「自分で描いて」みよう。
- 学んだことは、一度で覚えようとせず、「思い出す練習(復習)」を繰り返そう。
- 完璧を目指さず、自分に合った方法で、学習プロセスそのものを楽しもう。
これらの工夫を続けることで、あなたのイラストは着実に上達し、表現の幅も広がるはずです。そしてその先には、上達したイラストをSNSで発表して多くの人に見てもらえたり、同人イベントで自分の作品を誰かの手に届ける喜びが待っているかもしれません。
この記事が、あなたの本棚で眠っているイラスト参考書を「最強の味方」に変え、楽しく、そして確実な上達への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
才能や結果を焦らず、昨日より少しでも成長した自分を認めながら、創作活動を続けていきましょう。応援しています!
身につけた画力で、次のステップに進みたい方は
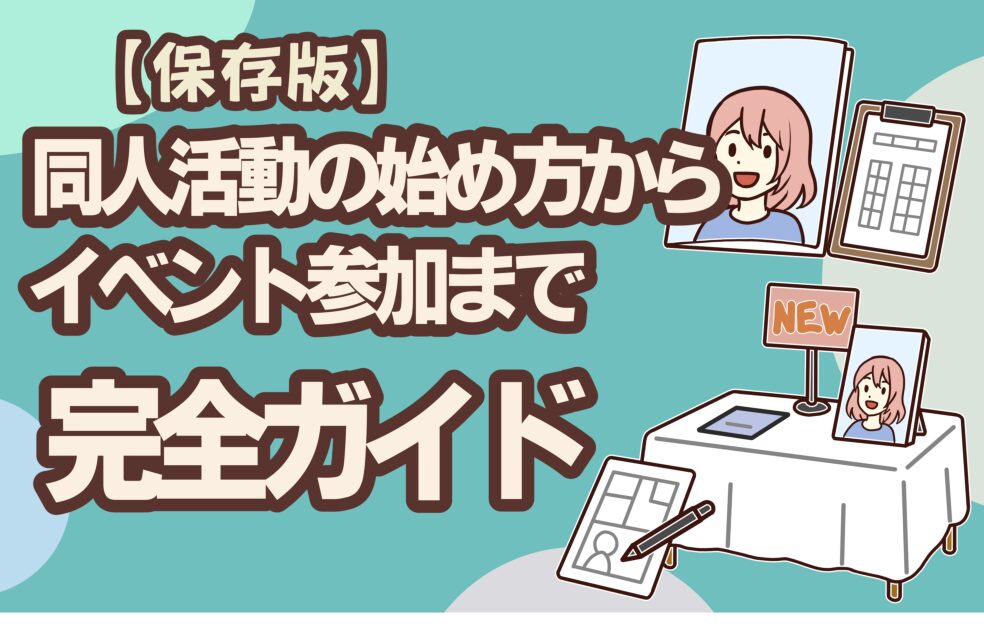
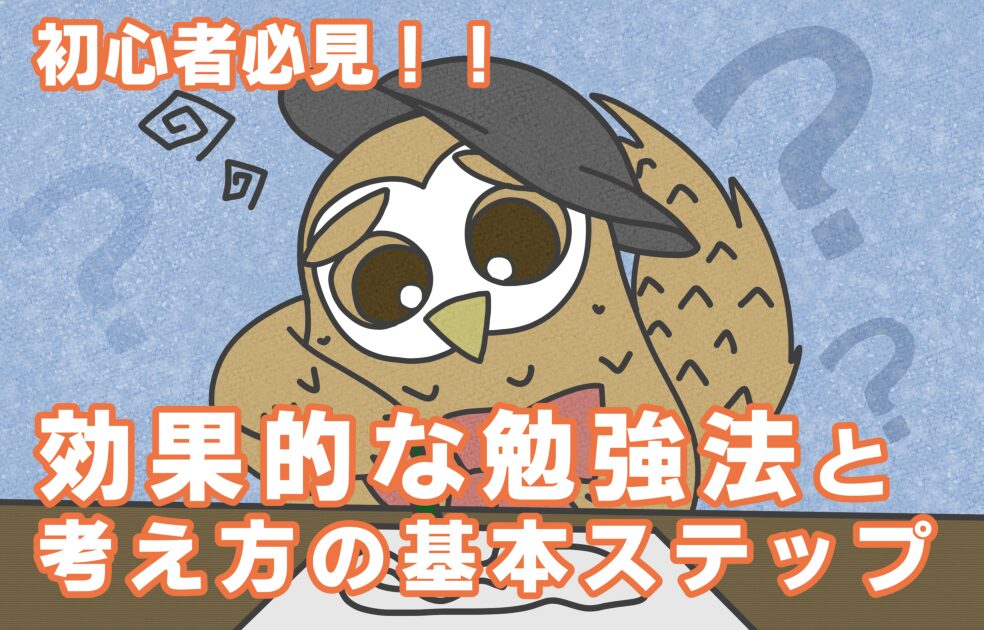
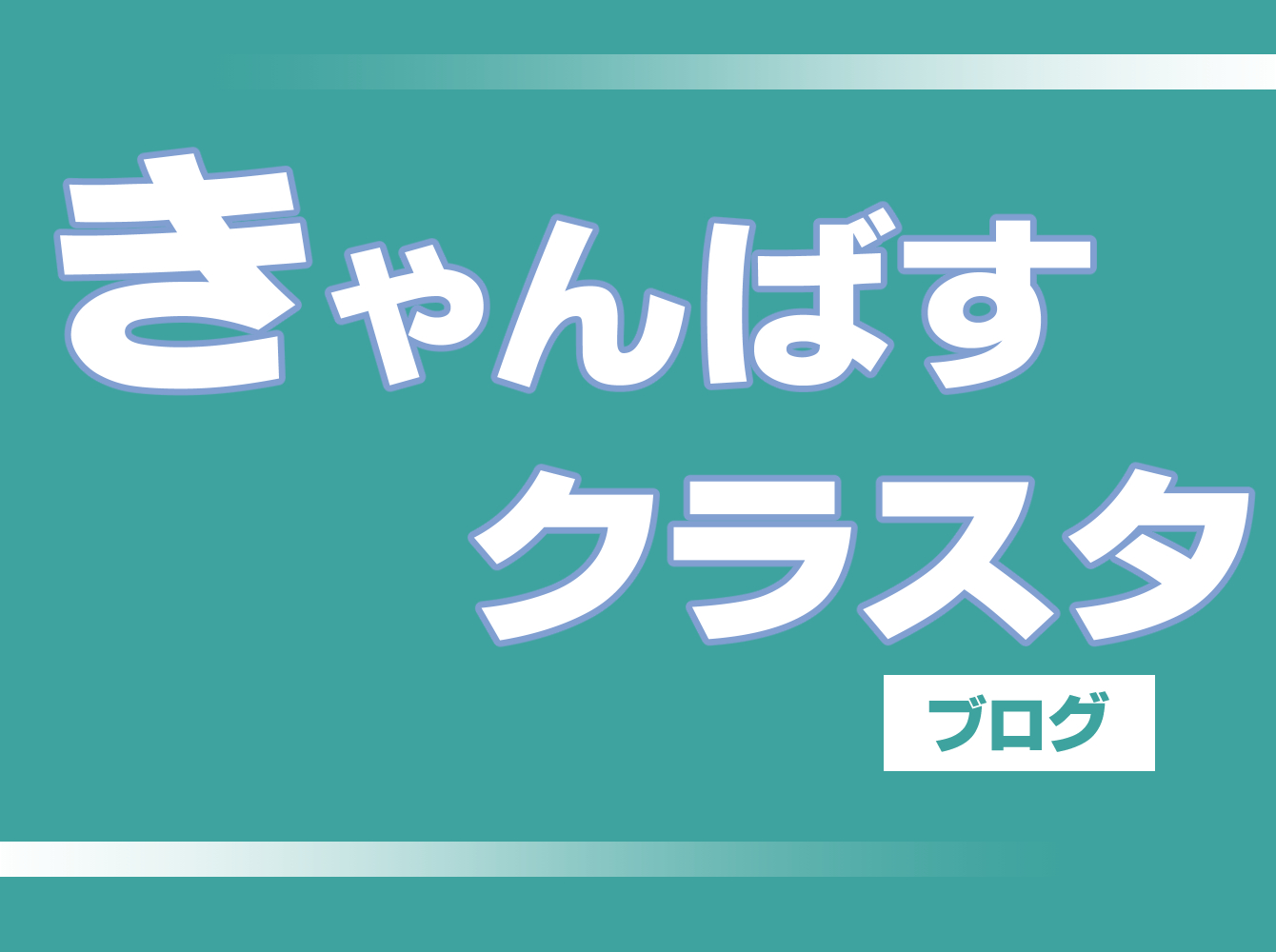
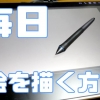


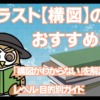
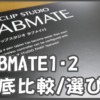
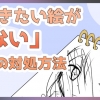

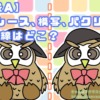
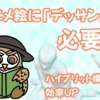
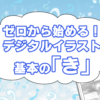
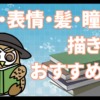
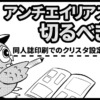
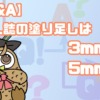
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません